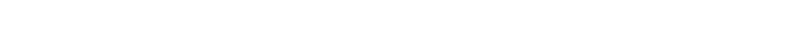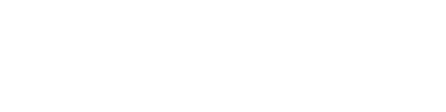ご相談の内容
私は、70代の男性です。
終活を始めました。
私の財産は、自宅土地建物と預貯金です。
妻と二人暮らしで、子ども2人は、独立して遠方に暮らしています。
私が亡くなった場合には、妻に不動産を取得させ、預貯金は妻と子ども2人に均等に分けたいと思っています。
遺言書の作成方法を教えてください。
回答
1 遺言書作成の方法
遺言の方式としては、大別すると、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
遺言書は、せっかく作成しても、遺言書の形式や遺言能力に問題があると、死後、遺言の効力が無効と判断される可能性があります。
たとえば、妻を中心に残された者同士で分け方を決めてもらいたいと考えて、遺言書に「私が死亡した後の財産の分配は妻に一任する」という表現を用いたとします。
このような遺言は、遺産の分割方法を共同相続人の一人に委ねる内容であり,民法908条の趣旨に反して無効であるとした裁判例(東京地裁平成17年10月20日平成17年(ワ)第14699号(判例秘書搭載))がありますので、妻と子供たちの間で遺言の効力について争いが生じた場合には、妻に遺産の分け方を任せることはできなくなります。
また、遺言の条項そのものが無効にはならない場合であっても、細かな文言や表現に解釈の余地があると、相続人間で解釈をめぐって争いになる可能性があります。
そこで、弊所では、ご自身の死後の紛争を減らすため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい、完成した公正証書は公証役場に保管してもらうことになります。
公証人は元裁判官や元検察官などの法律の専門家ですので、細かい文言のチェックや形式、遺言者の意思確認まで確認してくれるため、のちのちの争いが生じにくいというメリットがあります。
なお、民法の改正によって、自筆証書遺言保管制度ができました。
この自筆証書遺言保管制度を利用した場合、公正証書遺言と同様、後日の検認が不要となるというメリットがあります。
しかし、保管先である法務局は、あくまでも遺言書を預かってくれるだけで、内容のチェックまではしてくれませんから、この保管制度を利用するだけでは、ご自身の作成した遺言書の紛争リスクの有無を確認することはできません。
したがって、公正証書にせず自筆証書遺言を作成する場合には、少なくとも弁護士に相談して法的な問題点がないかどうかを確認してもらうべきです。
また、自筆証書遺言を作成したけれども、自筆証書遺言保管制度を利用しない場合には、相続人立会いの下、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
前述のとおり、公正証書遺言は、検認の手続きが不要ですので、例えば、後述のように他の親族の関与なく、相続手続きを進めることも場合によっては可能になるというメリットがあります。
2 不動産に関する遺言書作成の注意点
相談者は、妻に不動産を遺したいと考えています。
確実に妻に不動産を遺すためには、不動産について登記事項証明書の記載事項(所在や家屋番号など)を正確に転記して、どの不動産かを特定すること、そして、その不動産を「妻に相続させる」と明確に記載することが大切です。
これにより、後の名義変更手続きが円滑に進みます。
たとえば、前妻の子どもなど他の親族がいる場合、疎遠な親族との話合いや協力を得て名義変更手続きを進めないといけない場合があります。
しかし、上記のように明確に記載をした公正証書遺言を作成しておけば、妻が法務局に公正証書遺言を持って行けば、単独で登記名義を変更することが可能です。
面倒な手続きや関係者との話し合いを避けるメリットは大きいといえます。
ところで、相続人以外の場合、例えばお世話になった第三者に不動産の権利を譲渡したいと考えた場合には、第三者に「遺贈する」と記載をする必要があります。
相続人以外の人に対して「相続させる」との記載をすると遺言自体が無効となる可能性があるため、正確な表現をすることが大切です。
また、相続人同士で不公平があってはいけないと考えて、不動産を相続人3名で平等に3分の1ずつ共有して相続させたいと考えることもあるかもしれません。
このような遺言も有効です。
しかし、不動産を3人で3分の1ずつの持ち分割合で取得して、ひとたび共有関係になれば、相続人間で不動産の売却や修繕の方針が一致しない場合に、適切な処分や管理をできない状態に陥るリスクがありますので注意が必要です。
父母の死後に兄弟間で不仲になるということもありえますので、その場合のリスクを考えて、不動産は一人に相続させ、他の相続人には、預貯金から不動産の持ち分価格に相当する預貯金を取得させる方が、将来的な紛争回避という観点からは、望ましい場合もあります。
この場合は、不動産の適正な評価額を取得して、不動産持ち分のかわりに渡す代償金の額を決めることが大切です。
3 特定の相続人に不動産を相続させる遺言の注意点
特定の相続人、たとえば妻に不動産を相続させるとの遺言書を作成したとしても、実際に遺言者が死亡して相続が開始すると、他の相続人から不満が出てくることはよくあります。
その中でも、相続の前にすでに遺産の一部を受け取っているという主張はよくあります。
また、特定の相続人がもらいすぎているという主張もよくあります(これらの主張は、「特別受益」の主張と言います)。
そこで、遺言書を作成する場合には、生前の贈与を含めて、当該遺言の内容が、遺留分権利者の遺留分を侵害していないかという点には注意をする必要があります。
遺留分侵害額は金額で評価されますので、不動産の場合は、特に不動産の価値を公平に評価して、それをもとに遺留分侵害額を算定すべきです。
また、生前の贈与を特別受益として考慮してほしくないと考える場合は、遺言書に、特別受益については「持ち戻し免除する」という意思表示をきちんと記載しておくことも検討すべきです。
なお、婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産が遺贈・贈与された場合、持ち戻し免除の意思表示が推定されますので、あえて持ち戻し免除の意思表示までは不要とも考えられますが、あくまでも推定なので、他の相続人に争われる余地があるのであれば、明確に記載しておいた方が得策です。
4 まとめ
以上、遺言書作成の留意点、不動産に関する遺言を中心に解説しました。
我が国の相続では、不動産が遺産の中心を占める財産となることが多いですので、不動産を誰に相続させるのかとともに、不動産の価値をどのように評価して、不動産を取得できない相続人の不公平感を、いかに払拭して、みなが納得できる遺言書を作成するかということについても留意すべきとえます。
なお、前述のとおり公平を考えて全員の共有にするという解決は、特別な事情がない限り、お勧めしません。
不動産の遺言作成に際しては、専門の弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
遺言を通じて、希望する遺産の処分や分配を実現し、将来の紛争を回避する一助となることでしょう。