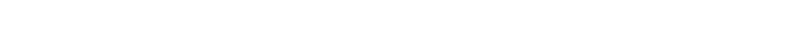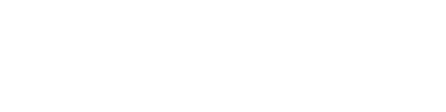1 遺留分とは
被相続人は、本来、自分の財産を自由に処分することができます。
しかしながら、民法は、相続の場面では、残された相続人の生活保障などを考慮し、被相続人が遺言によってその財産を処分する自由を一部制限し、一定の範囲の相続人について、一定額の財産を取得することができる利益を保障しています。
このような仕組みを遺留分と言い、民法によって遺留分を保障された者を遺留分権利者と呼びます。
2 遺留分権利者
このような遺留分は、全ての相続人に認められているわけではありません。
民法1042条1項は、「兄弟姉妹以外の相続人」について遺留分がある旨を定めています。
つまり、遺留分がある相続人(遺留分権利者)は、配偶者、子(及びその代襲者、再代襲者)、直系尊属となります。
被相続人の兄弟姉妹は、相続人ではあっても、遺留分はありません。
なお、相続開始時に胎児であった者は、その後、出生することで相続開始時点に遡って権利能力があったものとみなされるため、被相続人の子としての遺留分を有することになります(民法886条参照)。
3 遺留分の放棄等について
本来、遺留分を有する相続人であったとしても、相続欠格(民法891条)・廃除(民法892条、893条)・相続放棄(民法938条)などにより相続権を失った場合には、遺留分も失います。
また、遺留分を放棄することも可能です。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条)。
4 遺留分の割合(遺留分率)
民法は、相続財産全体に対する割合の形で遺留分権利者全員に留保されるべき財産の範囲を定めています。
これを総体的遺留分と呼びます。
総体的遺留分の割合(総体的遺留分率)は、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1とされています(民法1042条1項)。
この総体的遺留分率に個々の相続人の法定相続分割合を乗じたものが、それぞれの遺留分権利者の有する遺留分(個別的遺留分)となります。
個別的遺留分の算定式は、次のとおりに示すことができます。
5 遺留分算定の基礎財産
上記の式のとおり、個々の遺留分権利者が有する個別的遺留分を算定するにあたっては、まず遺留分の算定の基礎となる財産の範囲を確定する必要があります。
そして、この基礎財産の範囲は、民法1043条以下によって、次のとおり定められています。
- 被相続人の債務額
6 遺留分侵害額請求権
上記のとおり、個々の遺留分権利者は、各自に留保されるべき個別的遺留分を有しており、これが被相続人の遺言による遺贈等によって侵害された場合には、遺留分を侵害した受遺者等に対して、遺留分が侵害されたことを理由として、その侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利を有します(民法1046条)。
この権利を遺留分侵害額請求権と言います。
遺留分権利者は、この遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分を侵害した者から金銭の支払いを受けることで、自己の遺留分を確保することができるのです。
この遺留分侵害額請求権は、必ずしも裁判上行使する必要はなく、相手方に対する意思表示によって行使することができます。
もっとも、遺留分侵害額請求権は、①遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します(民法1048条前段)。
また、相続開始から10年が経過したときも同様に遺留分侵害額請求権は、行使できなくなります(同条後段)。
このように遺留分侵害額請求権には、権利を行使することができる期間に制限が設けられています。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使する際は、期間内に権利行使したことを後日証明することができるように、内容証明郵便等を用いて書面で通知をする必要があります。